自民と公明の連立に亀裂しています。
高市氏との確執、創価学会信者の動揺、そして「政治とカネ」が静かに決裂を導いた激震です。
この記事では、双方の陣営の思惑など深読みしていきます。
創価学会が自民に三行半?

10月10日に衝撃が走りました。
「沈黙の決裂」公明党が自民党に送った最後のサイン
2025年10月、自民党と公明党の連立関係が静かに終焉を迎えようとしています。
しかし、テレビも新聞も「政治とカネ」や「政策の不一致」といった表層的な理由ばかりを並べ、肝心な“裏の構造転換”には触れようとしていません。
実はこの別れは、26年続いた信仰と政治の橋渡しが崩れた瞬間であり、創価学会の信者たちにとっても「出口を失う」事態だったのです。
その引き金を引いたのは、他でもない高市早苗氏の“沈黙”でした。
高市の「譲らない戦略」が公明を自ら去らせた?
高市氏は、就任直後から公明党との距離を意図的に広げていた様にもみえます。
7日の斉藤鉄夫代表との会談では、公明が求めた「企業・団体献金の規制強化」について、あえてノーコメントを貫きました。
靖国参拝、外国人政策、裏金問題——いずれも公明が譲歩を求めたが、高市氏は一切応じませんでした。
これは単なる強硬姿勢ではないではありません。
「譲らないことで、相手に去らせる」という高度な政治技法のようです。
怒号も声明もなく、ただ淡々と関係を終わらせる。
まさに“沈黙の決裂”なのです。
公明党はこの「サイン」を見逃しませんでした。
対照的に自民党執行部はその意味を理解せず、旧安倍派の萩生田氏を幹事長代行に起用するなど、さらに公明との距離を広げてしましました。
麻生太郎副総裁を筆頭に、公明とパイプを持つ人物は皆無です。
公明関係者は「本音で話せる人がいない」と漏らしています。
信者の本音と公明の焦りを深読み!サイン

2025年10月10日に自民党と公明党の連立関係が静かに終焉を迎えました。
創価学会の信者たちが「出口」を失った
公明党の焦りの本質は、理念ではなく「票の行方」にある様子です。
創価学会の信者にとって、公明党は「信仰の出口」だったのです。
特に、自民との連立は、信仰と政治をつなぐ橋だったのです。
しかし、池田大作名誉会長の死去(2023年)以降、信者の熱は急速に冷めていました。
高齢化も進み、選挙への動員力は低下してます。
2025年7月の参院選では、改選14議席から8議席に激減してしまいました。
比例票も521万票と、ピーク時の862万票から4割減となっています。
この状況下で「誰に投票すればいいのか」「どこを応援すればいいのか」という疑問が信者の間に広がれば、組織票は崩壊に結び付きかねません。
公明党が連立離脱に踏み切れない最大の理由は、信者の“出口”を失わせる恐怖なのです。
さらに、学会内部では高市氏への“アレルギー”が強まっているのです。
タカ派的な姿勢、靖国参拝、外国人排除的な政策は、学会の理念と真っ向から対立するのです。
信者の間では「連立離脱も辞さず」という声が高まり、地方組織からも反発が出ていたのです。
メディアが報じない「終わりの儀式」
10日の高市・斉藤会談は、交渉ではなく“終わりの儀式”となりました。
すでに結論は出ており、形式的な確認に過ぎないようです。
声明もなく、怒号もなく、ただ静かに一つの時代が終ってしましました。
この沈黙の裏側で進行しているのは、「自公の終焉」ではなく「保守政治の再設計」なのです。
高市氏は国民民主とのパイプを強化し、創価学会の信者票に頼らない新しい保守連合を描こうとしている様子です。
そして、公明党は「信仰の出口」を再構築できなければ、政治的にも宗教的にも求心力を失うのではないでしょうか。
「沈黙の決裂」公明党が自民党に送った最後のサイン

創価学会の信者にとって、公明党は単なる政党ではなく「信仰の出口」でした。
選挙活動は功徳の一部であり、政治参加は信仰実践の延長線上にあったのです。
しかし、連立の亀裂が表面化すると、信者は次のような心理状態に陥ります。
- 「誰を応援すればいいのか分からない」 → 自民党との連携が崩れると、信者の行動指針が消失。組織票の崩壊につながる。
- 「信仰と政治がズレてきた」 → 高市氏の靖国参拝や外国人政策は、創価の平和主義と相容れない。信者の内面に葛藤が生まれる。
- 「学会の指示に従うべきか、自分の良心に従うべきか」 → 特に若い世代や都市部の信者は、政治的価値観が多様化しており、組織の一枚岩ではなくなっている。
この「出口喪失」は、単なる票の減少ではなく、信仰の実践形態そのものが揺らぐ構造的危機です。
「沈黙による決裂」言葉なき戦略的離縁
高市氏が公明党との交渉で「ノーコメント」を貫いたのは偶然ではありません。
これは「言葉を使わずに関係を終わらせる」高度な政治技法です。
この沈黙には以下の戦略的意味があります。
- 「譲歩しないことで、相手に去らせる」 → 自ら手を汚さず、相手に決断させることで責任を回避。
- 「怒号も声明もない、静かな終焉」 → メディアに騒がれず、支持層にもショックを与えない。世論操作としても有効。
- 「関係修復の余地を残さない」 → 公明党が「サイン」を送っても、自民党執行部は反応せず。関係は自然消滅へ。
この「沈黙の決裂」は、表面的には穏やかですが、実際には関係修復不能な断絶を意味します。
しかも、信者や支持層には「いつの間にか終わっていた」という印象を残すため、反発も最小限に抑えられるます。
🧩構造的な意味:信仰・政治・組織の三重崩壊
この2つの視点が交差すると、次のような構造的崩壊が見えてきます。
最後に簡単な表にまとめてみました。
| 崩壊対象 | 具体的現象 | 影響 |
|---|---|---|
| 信仰の出口 | 信者が「誰に投票すべきか」迷う | 組織票の崩壊、信仰実践の空洞化 |
| 政治的連携 | 自公の連立が沈黙のまま終焉 | 保守勢力の再編、国民民主への接近 |
| 組織の求心力 | 公明党が信者の支持を維持できない | 地方組織の分裂、若年層の離脱 |
まとめ
高市氏の沈黙が公明との決裂を招き、創価学会信者は「政治の出口」を失ないました。
信仰と政治の橋が崩れ、組織票も揺らぐ中、自民はそのサインを見逃し、保守再編の主導権を失うリスクを抱えててしましました。
今後の政治情勢は、私たちの生活にも大きな影響を与えそうです。
ますます、政権の行方から目が離せません。
長い間お付き合いいただきありがとうございました。
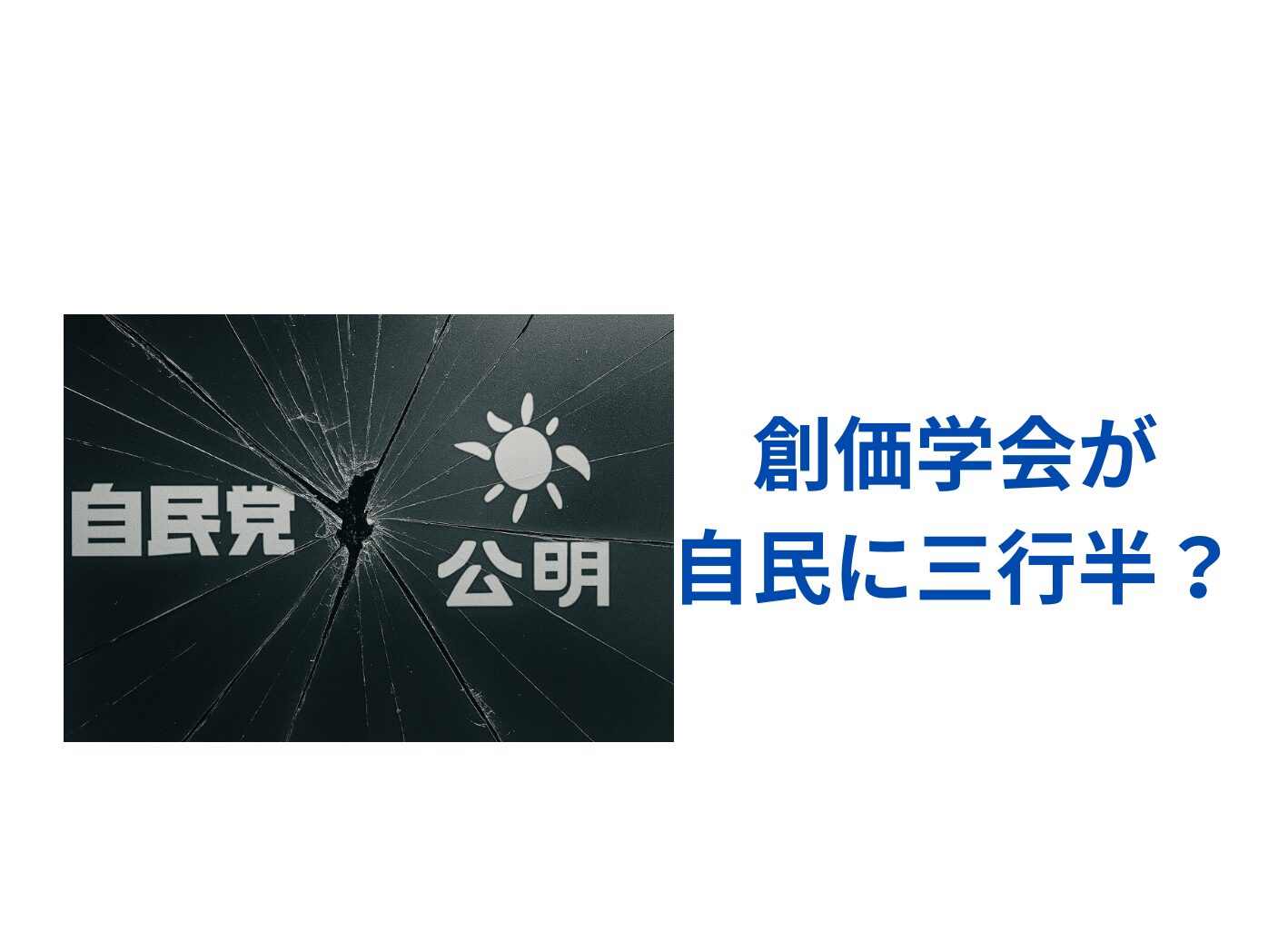
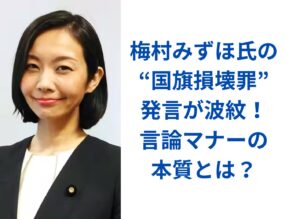
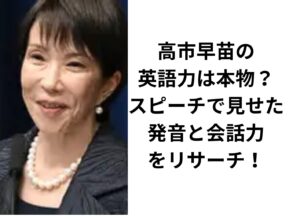

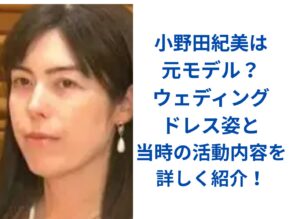
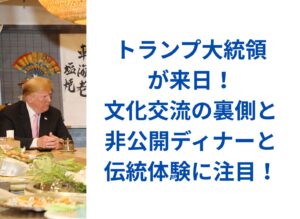

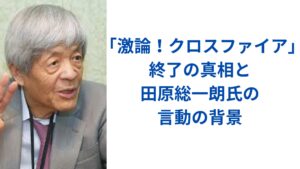
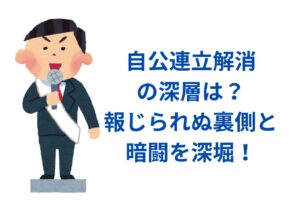
コメント