歌手・シンガーソングライターとして今もっとも注目される存在、幾田りらさん。
ユニット「YOASOBI」のボーカル“ikura”としてだけでなく、“幾田りら”という個としての表現にも定評があります。
今回は、メディアであまり語られない彼女の家族背景、幼少期の海外体験、下積み時代という歌の原点を“裏話”を交えて深掘りし、その人気の理由に迫ります。
幾田りらの知られざる素顔とは?
「YOASOBI のボーカル “ikura” として知られ、ソロ名義でも存在感を放っている幾田りらさん。
その明るくキャッチーな楽曲からは想像しにくいかもしれませんが、彼女のキャリアには「家族との音楽的絆」「幼少期の米国体験」「路上ライブからのスタート」といった、メディアではあまり深掘りされない“ニッチなエピソード”が数多く存在します。
今回は、その一側面を掘り下げ、引いては「なぜ彼女の歌声が“共感される”のか」を整理してみたいと思います。
幾田りらさんの魅力は、「幼少期からの音楽環境」「身体に染みついた英語/洋楽的感覚」「リアルなライブ経験」という三つの土台があいまって、「言葉と歌声で“今の自分”を語る力」へとつながっている点にあります。
言い換えれば、彼女の歌には“誰かの物語を代弁する”のではなく、“自分自身が語る”リアルが宿っており、だからこそ聴き手の心に届くのです。
家族・幼少期・歌の原点を裏話で深掘り!
幼少期に刻まれた“音”の記憶
歌手・シンガーソングライターとしてますます存在感を高めている幾田りらさんですが、彼女の歩みを振り返ると、幼少期から“音”とともにあったことが浮かび上がります。家族の中に自然に音楽があったからこそ、「歌うこと」が特別ではなく、日常そのものだったのです。
まず、彼女自身が語るように、「家の中は、いつも音楽であふれていて、父はリビングでよくギターを弾いて歌っていたので、私も物心がついた頃には『歌手になりたい』と思っていました。」(『マイナビニュース』インタビューより)マイナビニュース
この言葉が示すのは、歌う・作る・伝えるという体験が家庭の“当たり前”として存在していたということです。
次に、幼児期の海外体験も見逃せません。
りらさんは、3歳まで米国・シカゴで暮らしていたと言います。
「私は3歳までアメリカに住んでいたこともあって、幼少期から洋楽を聴いて育ちました。…ディズニーチャンネルで色んな作品を見て、そのサウンドトラックを買って英語で完コピしたり。その頃の影響が今の自分の歌い回しにも出てるのかなって思います。」(Billboard Japanインタビューより)
この経験から、「言語や文化を超えて音を感じる」という感覚が、歌声にも表れていると考えられます。
家族が紡いだ“歌と物語”
家庭での出来事が、彼女の表現の原点となっています。家族の中で「歌を贈る」という行為が習慣化されていたのです。たとえば、彼女はこんなエピソードを語っています。
「父が“ホワイトデーに曲をプレゼントしたいから、バレンタインは歌詞をつくってほしい”って母に頼んでいたり」
引用元:文春オンライン+1
このように、言葉と旋律を通じて気持ちを伝える“贈り物”が家庭で繰り返されていたことは、シンガーソングライターとしての彼女の根幹を成していると言えます。
さらに、彼女の最初の曲作りは小学校6年生のとき。「別の学校に行ってしまうお友達に対してプレゼントとして私も曲を贈ろうって思って、それで作ったのが自分にとって初めての曲」という言葉からは、歌を通じた“人とのつながり”を自然に手にしていたことが読み取れます。
この“子供の感覚”で曲を作る行為こそ、後の「自分の言葉で歌う」スタンスにつながっているのです。
下積みから見えてきた表現者としての覚悟
家庭や幼少期の環境が土台なら、その上で“立つ”場所を自ら見つけたのが、路上ライブなどの実践経験です。
幾多リラさんはこう語っています。
「15歳のとき、まだ一歩も踏み出していないことに焦り始めた。ライブハウスを回ったり、路上ライブもやって」
引用元:文春オンライン
この言葉には、デビューの前から「自分を表現しなければならない」という自覚が感じられます。東京・吉祥寺の商店街や井の頭公園で歌っていたという当時の体験は、観客の反応も、時には母親の見守りも含めて彼女の“リアルな表現力”を鍛えたのでしょう。
また、家庭で培った「言葉を自分でつくる」「音を届ける」という土壌は、ユニット YOASOBI での活動、そしてソロ活動へと自然に拡がっていきます。
彼女自身は、「幼少期からの自分を歌うことが軸になっている」と語っています。
この覚悟が、表面的な歌手像ではなく、「表現者」としての幾田りらを支えているのです。
なぜ幾田りらの歌声が“届く”のか
では、なぜ彼女の歌が多くの人に“届く”のでしょうか。その理由は、構成されたバックグラウンドにある“リアルさ”と、“言葉と音が一致する”瞬間にあります。
まず、前述のような家庭環境・幼少期の経験・下積みの時間が、彼女の歌に「物語=背景」を持たせています。そして、その背景を言葉にし、音に変えて歌うとき、「語りではなく歌う」という形に落とし込まれることで、聴き手は“ただ聴かせられている”のではなく“共鳴している”という感覚を得ます。
また、幼少期に英語圏の文化に触れていた経験が、「歌のフレーズに英語的な間」や「音の余白」をもたらしているという指摘もあります。
この“音楽を言語的・文化的に超えて捉える感覚”は、国内のポップスにありがちな“模倣”とは一線を画し、彼女の歌声を際立たせています。
さらに、歌詞を自ら書き、メロディーとともに届けるスタイルが、“消費されるポップス”ではなく、“表現される歌”という質を生み出しています。
そして、この質こそが、メディアで大きく取り上げられる派手なエピソードではなく、「曲を贈る」という極めて個人的な記憶の中から紡がれてきたものだと言えます。
幼少期のエピソード
“卒業する友人にギターでサプライズ曲を歌った”というエピソードは比較的知られていますが、もう少しマイナーなものとして、彼女が 「洋楽サントラを英語で完コピしていた」 という幼少期の習慣があります。
具体的には、シカゴ時代にディズニーチャンネルで見ていた作品のサウンドトラックを購入し、「歌詞を目で追いながら英語で歌っていた」というものです。
このエピソードが示しているのは、彼女にとって“歌”が幼い頃から「音と声を再現する」遊びであったということ。
つまり、彼女が歌うときに自然と出る“イントネーション”や“英語的なフレーズのノリ”は、単なる技術ではなく、身体に染み込んだ“歌の原体験”から来ています。
このあたりの“遊び的な習慣”が、後のプロとしての“歌を届ける力”に静かに影響を及ぼしているのではないか、と私は思います。
まとめ
幾田りらさんの歌には、「家庭で息づいた音」「幼少期の海外体験」「実践としてのライブ活動」という三つの土台が確かにあります。
そして、それらは“歌手という職業”ではなく、“表現者として自分を歌う”という軸へと収束しています。
だからこそ、彼女の声には「ただ上手い」ではなく、「聴いてしまう」力があります。
歌の裏にある根っこの部分を知った今、次に彼女の曲を聴くときは、旋律だけでなく、その歌がどこから来たのか・何を語ろうとしているのかに意識が向くはずです
お付き合いいただきありがとうございました。
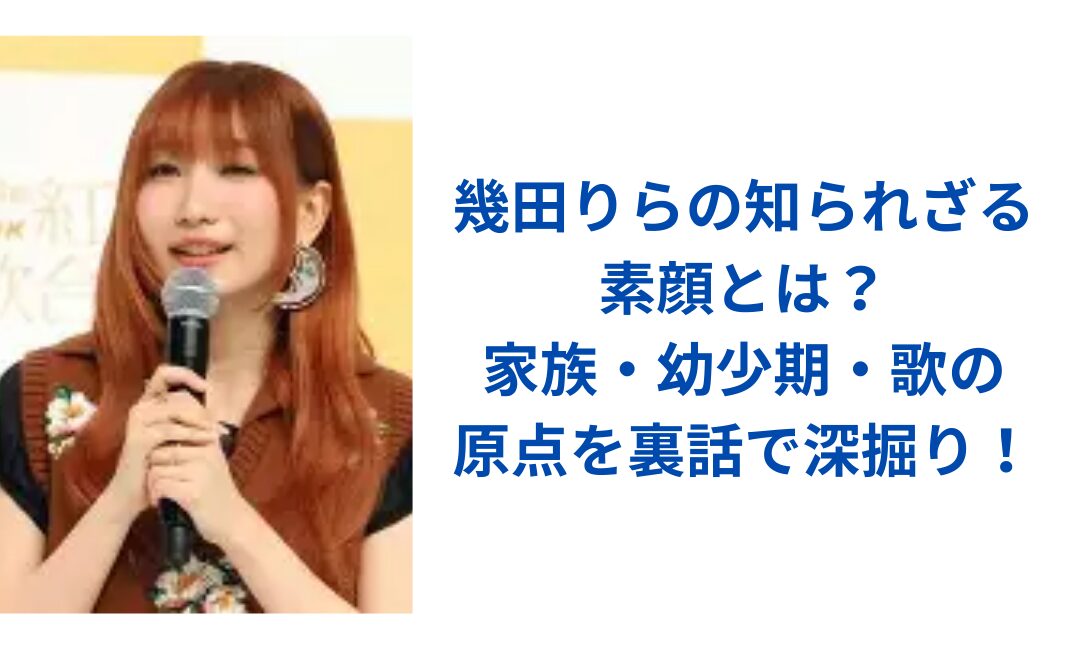








コメント